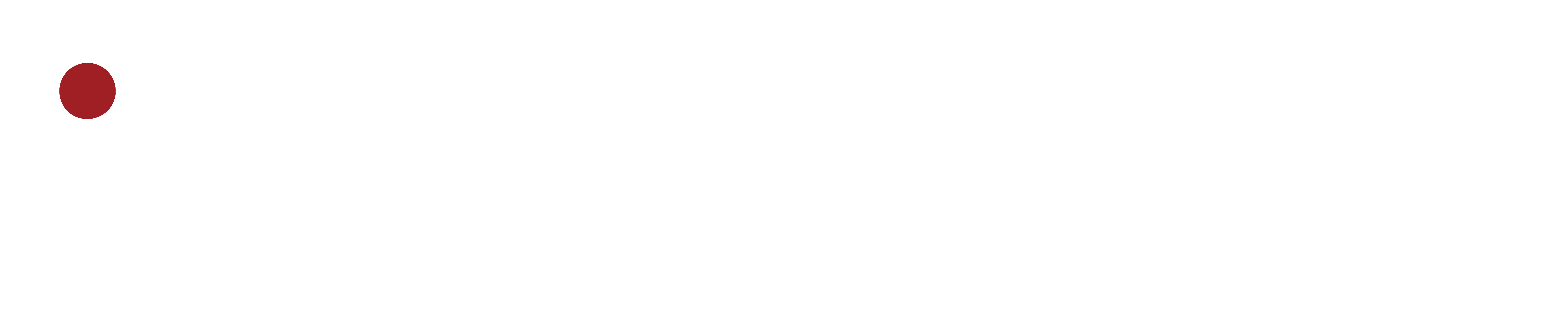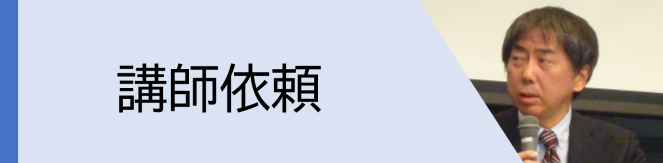漫言放語 №63
新しい年に思うこと
年賀状の現状
「時節柄、メールでの賀状。心広くお許しください」
元旦に届いた年賀状である。メールによる年賀状が広がりつつあるのだろう。そう言えば、昨年は「今後は年賀状でのご挨拶を控えさせていただくこととしました」と書かれた年賀状が届いた。「今後とも末永いおつきあいをお願いします」と書かれていたが、年賀状だけの付き合いをしていた人とは二度と付き合う機会はないだろうと思いながら文面を読んだ(年賀状のやりとりだけではあるが、大切な人だと考えているからこそ出していた)。
一年間の集大成としての年賀状
私はと言えば、時代に逆らって?相変わらず年賀状の作成にかなりの時間をかけている。今年の年賀状のフォルダには、次の6種類の年賀状が保存されている。
A 孫 B 娘 C 親族 D (かつての)上司・同僚 E 友人 F 仕事
当然、内容はかなり異なっている。特に時間をかけているのはFである。教育関係の仕事で切磋琢磨してきた人に出す年賀状である。
Fの年賀状を書き始めたのは、若いころ追い続けていたM氏の影響が大きい。
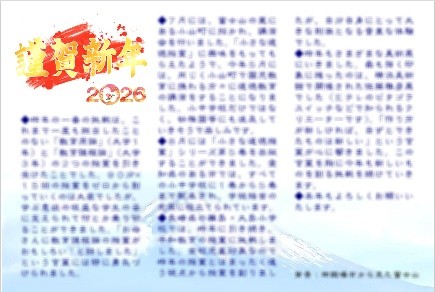
M氏の年賀状には、裏面いっぱいに一年間の仕事のことやエピソードなどが小さな文字でびっしりと書かれていた。それ自体が一つの読み物になっていて、しかも読み応えがあった。年賀状に対するイメージが180度変わった。
右に示したのは今年の年賀状である。最後の余白に直筆のメッセージを書く。読み手にとって何らかの意味のあるエピソードを書くためには、それなりの一年間を過ごすことが大切であり、そういう意味で、年賀状は、一年間の集大成ともなっている。
書くということ
女優の上白石萌音さんは、書くことを大切にしている人である。
PILOTの新聞広告で次のような話をしていた。
いつでも手軽に発信できるデジタルの時代だからこそ、誰かを思ってわざわざ「筆をとる」ことの特別感やうれしさは、ますます強く感じられるような気がします。書くということは、人を大切にすることでもあると思います。
この言葉に強く共感した。
これからも人を大切にしていきたいと改めて思った元日であった。
おすすめリンク集
新着情報
開催予定
| 2026年1月31日(土) | 14:00~16:30 | 第9回 SDK特別定例会(会員でない方も参加できます) |
|---|