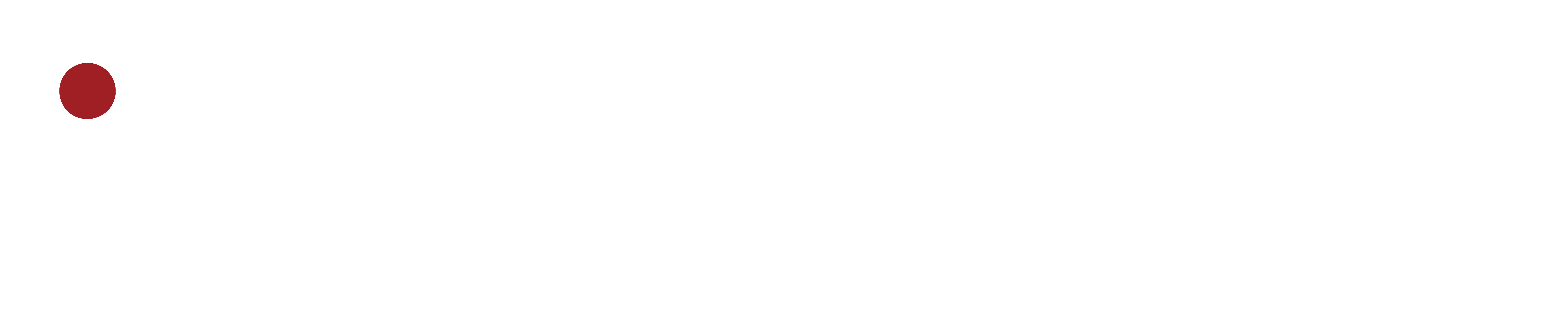読書日記~5月~

どうして「体育嫌い」なんだろう
著者 井谷惠子ほか 大修館書店 2025年
『声にならない声を聞くために』
どうして「体育嫌い」なんだろう?
あなたは、この問いにどのように答えるだろうか。
本書を読むまで、ただ単に「運動が苦手だから」くらいにしか考えていなかった自分の浅はかさに気づかされる。
「はじめに」で、井谷氏は次のように言う。
「体育嫌い」が本人のせいではないとしたら、何が原因なのか。スポーツ好きであっても体育で嫌な思いをすることがあるのは、どうしてなのか。それらを明らかにするために、この本では「体育嫌い」当事者の声を、そして「体育の当たり前」を、ジェンダー・セクシュアリティの視点から考えていきます。
「体育嫌い」当事者の声として、次のようなものが取り上げられている。
「楽しくチームスポーツしたいけれど、失敗した時のみんなからの視線が怖い」
「体育の目的は『うまくなること』だけだから、できない自分は成績が悪くてもしかたがないと思っていた」
「男女別でチーム分け・決められた種目があって、自分はいない前提なんだと思った」
私たち教師には、子どもたちのこんな声が聞こえているのだろうか。
「体育への恨みつらみ川柳」で紹介されたという次の作品も胸に刺さる。
持久走 周回遅れで 拍手され
この作品の投稿者は、「止めてくれ、敗者に拍手なんていらない!誰も見ないでって。あれが、本当にマラソン大会で一番屈辱の瞬間だった」という経験を吐露しているという。
最下位でもゴールまで走り続けなければならない子どもに拍手を送ることを美談にしてしまっている教師の間違った価値観がどれだけ子どもを苦しめてきたことだろう。
「体育嫌い」の子どもたちへの配慮だけではなく、教育全般に深く関わる重要な視点を学ぶことができる一冊である。
読書日記~2月~

『世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方』
越川 慎司 株式会社クロスメディア・パブリッシング 2024年
『土日の過ごし方を意識する』
みなさんは休日の土日をどのように過ごしていますか?
土日を過ごすときにあることを意識することで、仕事のパフォーマンスを高める教養と休養の両方を手に入れ、より充実した生活を送ることができることを本書で学びました。
それは、
土日を戦略的に使い分ける意識をもつこと
です。土日が休みの場合、その二日間を「まとまった休日」ととらえているのではないでしょうか。本書では土日を次のように戦略立てて意識して過ごすことが書かれていました(110,111ページ)。
土曜日…「チャレンジデー」と位置づけて、自分の趣味や家族との時間を楽しむだけでなく、新たな人間関係を構築したり、興味のあるワークショップやセミナーに参加したりするなど、未体験のことに積極的に挑戦することを意識。
日曜日…「リフレッシュデー」と考えて、運動や読書、ヨガや瞑想などを通して、身体とメンタル、脳のリフレッシュを図ることを意識。
(筆者該当ページを要約)
特に土曜日は、リスキリング(新たな仕事や未体験の分野にチャレンジするために、スキルや知識を獲得すること)に注力することで、学びの時間を確保できます。
これを読んで土曜日は、日頃SDK会員が実践している「小さな道徳授業」づくりやSDKのセミナーの予定を事前に入れておこうと思いました。小さな道徳の授業プランを思いつくのは、行ったことのない場所に行ったときと初めての体験をしたときに、思考が刺激されるので新たなことに積極的に挑戦することができます。またSDKのセミナーも土曜日に開催されることが多いので、難しく考えなくても、土曜日を戦略的に使うことができそうだと思いました。
「行けるときに行こう」「やれるときにやろう」では、いつまで経っても実行できません。休日を、「平日の疲れをとるための時間」として捉える見方を脱し、土曜日に予定をあらかじめ入れておく工夫をして、充実した休日を過ごしていく準備をしていこうと思います。
読書日記~12月~

『ボクの彼女は発達障害 ドタバタ同棲生活編』
著者 くらげ 漫画 寺島ヒロ Gakken 2024年
『知らない世界を知ることの重要性』
「駅にハトがいたから追っかけてたら電車に乗るのを忘れちゃってさ」
これが、待ち合わせ時間に大幅に遅れてきた人の理由だったとしたら、あなたはこの人をどう思うだろうか。多くの人は、「ありえない理由で遅れるとんでもない人」と思うことだろう。
しかし、本書を読むと、これも発達障害の人の特性であることに気づかされる。
このような彼女をもつ“くらげ”さんは、次のように対応する。
例えば、一緒に行くイベントが13時開始なら、最寄り駅に11時の合流にします。
そうすれば、まぁ、2時間の余裕は生まれるわけでして。
このほかにも、私たちが想像もつかないエピソードの数々が綴られている。
例えば、次のような話である。
人にものを頼むのにも怖さを覚える
なぜ怖さを覚えるのだろうか。
彼女の“あお”さんは次のように言う。
「だって、人に頼むと怒られるし、ずっと『自分のことは自分でしなさい』って教わってきたから」
「お願いしても『それはダメ』とか言われるから頼まないほうがマシ」
このエピソードから考えさせられるのは、教師のちょっとした一言も「人にものを頼むことに対する怖さ」を生み出している可能性があるのではないかということである。
教室には、さまざまな特性の子どもたちがいる。
知らない世界(発達障害の人の特性)を知ることによって、子どもたちの言動を判断するものさしが少しだけ広がり、ちょっとやさしくなれるような気がする。
読書日記~8月~

『相談しがいのある人になる 1時間で相手を勇気づける方法』
下園壮太 講談社 2014年
『相談しがいのなかった私の話。』
先日、仕事で付き合いがある後輩から「相談に乗ってもらえませんか」と言われた。
どうやら、仕事のことで悩んでいるようである。年の近い仲間ではなく、私に相談してくるということは、きっと「答え(解決策)」を求めているのだろう。しばらく話を聞いた後、「自分だったら、こうするかな」と、過去の経験を踏まえながら話した。
しかし、後輩の様子がおかしい。どんどん顔が曇っていくのである。
頼ってくれたはずの後輩が、目の前で元気を無くしていく様を見て、私は心にトラウマ級の打撃を受けた。
「何か間違っていたのではないか」
藁にも縋る思いで、書籍を検索する。出合ったのが本書である。
本を開くと、心理カウンセラーの下園さんの言葉が、次々と心に飛び込んでくる。(28ページ)
あなたは相談を受けるときにどんなことを考えているでしょう。「相手は自分を頼ってくれた。頼りがいのあるところを見せたい」「問題を即、解決してよく見られたい」などと思っているのではないでしょうか。そういう意識が強いと、どうしても「すぐに解決策を出してやろう」としてしまいます。日常の多くの相談はこのような対応でカバーできるでしょう。ところが、この対応では通用しないこともあるのです。とくに「悩みの深い相談者」の相談を受けるときには、十分な効果を上げられません。
胸に突き刺さるとはこのことである。結局私は自分のことしか考えていなかったのである。情けない。
では、どうすれば良かったか。簡潔に要約すると、
・ 「悩みの深い相談者」は、ややもすると、うつに近い状態なので、アドバイスよりも「味方でいる」という言葉かけが大切。
・ 「自分だったらこうする」→「あなたはできたかもしれないけど私はできない」のように、話し手の思い通りに受け取ってもらえないこともある。
・ 最初に●分間、傾聴する必要がある。(何分か気になる方は、是非本書を手に取ってみてほしい。)
読み終えた後、すぐに後輩と話し、小学生のような口調で自分の至らなさを謝った。
信頼が回復することはないかもしれない。
それでも、味方でいたいというメッセージは伝え続けたい、いつか「何かあったら先輩に相談しよう」と、また思ってもらえる日を待ちながら。
読書日記~4月~

『校長の力』
工藤勇一 中公新書ラクレ 2024年
『実践の背景にあるものも学ぶ』
宿題廃止。
定期テスト廃止。
固定担任制廃止。
これまで学校で当たり前とされてきたことを覆し、子どもの主体性を活かすための教育改革に取り組んだ工藤氏。その改革を行なった東京都の麹町中学校には、毎年数多くの訪問者が訪れ、その取り組みを真似しようとする学校も少なくないようです。
しかし、管理教育をやめて子どもの主体性を生かそうとすると、見た目では学級が荒れて見える傾向があり、その段階でこの方法はダメだと見切りをつけてしまう学校は、管理教育に戻してしまうようです。
学級の荒れが見えたときに、「見切りをつけ管理教育に戻してしまう学校」と「子どもの主体性を生かそうと取り組み続ける工藤氏」には、どんな違いがあるのでしょうか。
工藤氏は、言います。
学校の役割とは何か……僕自身は、学校とは「人間が社会の中でよりよく生きていくことができる力をつける場」だと考えています。…子どもたちがこの社会にはいろいろな人がいるという多様性を受け入れながら、自ら考え、自ら判断し、自ら決定し、自ら行動する力、つまり自立する力をつけていくことこそ、教育だと思います。学校は、その手助けをする場であり、教師たちの役割はそれを支援することです。(p46)
工藤氏には、「自立する力をつけていくことこそ、教育」「学校は、その手助けをする場である」という「教育哲学」があります。その哲学によって、学級に荒れがみえたとしても、その状況を受けいれ、主体性を生かそうとする取り組みを続けていくことができるのです。
近年の教育書のトレンドは、「具体的な方法論や技術」にあるといいます。しかし注意したいのは、技術や実践例を真似するだけでは、その効果は限定的、あるいは一時的であるということです。その背景にある「教育哲学」も学ぶことで、それを反映させるための方法を生み出せるようになるという点を常に忘れないようにしたいです。
読書日記~3月~

『子どもが「学びたくなる」育て方』
矢萩邦彦 ダイヤモンド社 2022年
『子どもの「やりたい」を引き出す』
ある小学校で、“探究ノート”という宿題が出されました。“探究ノート”とは、宿題のテーマを自分で考え、自分で振り返りをする宿題のことです。自分でテーマを考えるのが難しい子のために、「計算問題」「漢字の書き取り」「絵日記」「読書感想文」などのメニューが用意されていて、子どもたちはそれらのメニューの中から選んで取り組んでいたそうです。
皆さんはこの“探究ノート”に対して、どのような印象をもったでしょうか。
筆者はこの取り組みに対して、「これまでと変わらない宿題を『主体性があるかのように』『探究っぽく』させているだけ」と述べています。つまり、教師が本当の意味での「主体性」や「探究的な学び」を理解せずに取り組ませているため、子どもたちは「やりたい」ではなく、「やらされている」という状況から変わっていないのです。
では、子どもの「やりたい」を引き出すためには、どうしたらよいのでしょうか。
本書では、子どもが「学びたくなる」育て方について、次の3つが挙げられています。
「対話する」「探す」「やってみる」
また、第4章「やってみる」の中で、子どものやる気を引き出すために大切なことについて、次のように述べられています(174ページ)。
仕事でも、家事でも、趣味のことでも、自分なりの学びを楽しみ、学んだことを楽しんでアウトプットしていると、それを見ている子どもの好奇心や、やる気も育っていきます。
まずは自分自身が学びを楽しむこと、そしてその学びをアウトプットすることで、子どもの好奇心ややる気が育っていくのです。
先ほどの“探究ノート”も、まずは教師自身が自分なりの学びや探究してみたいことをアウトプットすることで、子どもたちのやる気に火をつけることができたかもしれません。
子どもだけでなく大人も「学びたくなる」、そんな1冊です。
読書日記~12月~

『絵本力―SNS時代の子育てと保育―』
浅木尚実 ミネルヴァ書房 2023年
『子どもを育てる絵本の力』
絵本にはどんな力があるのでしょうか。
このことを知っているかどうかで子育てに大きなちがいが出てくるのだ、ということを本書から学ぶことができました。
本書では、おとなになる前につけたい五つの土台として、次のようなものを挙げています。
愛着形成、自己肯定感、認知能力・非認知能力、ユーモアのセンス、思いやりの心
絵本の力は、この五つの土台の発達に深く関係しているのです。
例えば、絵本と自己肯定感の関係について、次のように述べられています(117ページ)。
子どもは、絵本の読み聞かせを受けながら、主人公に自分を重ね合わせ、少しだけ高いハードルを超えていく姿勢をイメージとして蓄積し、学んでいきます。読み聞かせのたびに、大人の愛情を伴いながら、自信を取得し自己肯定感を蓄えていくのです。
日本の子どもは自己肯定感が低いと言われますが、改善のヒントは絵本にあったのかもしれません。
本書には、長く読み継がれてきているすばらしい絵本がたくさん紹介されています。
いまさらですが、もう一度子育てをやり直したくなってきました(笑)。
読書日記~6月~

『スマホ依存が脳を傷つける デジタルドラッグの罠』
川島隆太 宝島社新書 2023年
『脳をなまけさせない』
先日、通勤で久しぶりに電車に乗った。
その車内でスマホを見ている人の多いこと。約8割以上の人がスマホを見ているのである。中には、スマホ依存という状態になっている人もいるのではないだろうか。スマホのおかげで確実に生活は便利になっている。今やスマホなしで生活する方が難しいのではないだろうか。
しかし、この状況に警鐘を鳴らす筆者は次のように言う。
自分で考えるのをやめ、思考することをスマホやAIにアウトソーシングする生活で、人は本当に幸せに生きることができるでしょうか?
(60ページ)
生活が便利になれば、人間の負担が減る。その分、人間の能力は落ちていると筆者は述べている。
つまり、スマホを使うことで脳をなまけさせており、結果として思考力は落ちてしまっているということである。私たちは何のためにスマホやAIを使っているのだろうか。
学校現場ではGIGAスクール構想として、一人一台タブレットの活用が進められている。今までにない学習に取り組みやすくなるのは確かに利点であろう。しかし、そのことによって失われるものがあるのである。
子どもたちにスマホやタブレットの利点や使い方を教えるだけでは、よき使い手にはなれない。生活を便利にしてくれる道具とどのように付き合っていくかを考え続ける姿勢をもつこと。つまり、道具に使われるのではなく、道具をどのように使うとよりよい生き方につながるかを考え続ける姿勢が大切であることを子どもたちに伝える必要があるのではないだろうか。
教育者として考えさせられる一冊であった。
読書日記~5月~

『限りある時間の使い方』
オリバー・バークマン かんき出版 2022年
『人生はわずか4000週間』
『人生はわずか4000週間。限られた時間をどう過ごすか?』
本の帯の衝撃的な言葉が私たちに問いかける。
年間約50週、人生80年だとしたときの時間のあまりの短さに私もショックを受けた。
しかし、限られた時間をどう過ごすかという大きな命題を前にしたとき、私たちは「どう効率よく時間を使うか」という頭になってしまうのではないだろうか。
イギリスの全国紙の記者として若手ジャーナリスト賞などを受賞したライターであり、この本の著者であるオリバー・パークマン氏は次のようにいう。
誰もが急いでいる社会では、急がずに時間をかけることのできる人が得をする。大事な仕事を成しとげることができるし、結果を未来に先送りすることなく、行動そのものに満足を感じることができる。(P.203)
日々の多忙感に負けて、満足感を得ていなかったとはっとさせられた。
「急がずに時間をかけることのできる人が得をする」という言葉に、巷にあふれる時間に対する認識と一線を画すと感じたのである。私にとって、大事な仕事とは何だろうと考えさせられた。
「道徳教育に関する書籍を出版したい」
「国語教育に関する書籍を出版したい」
「人生哲学・人間哲学に関する教養を身につけたい」
私は自分が成しとげたい大事な仕事について長考し、このように手帳にしたためた。
書籍を出版できるくらい実践を積み重ね、言語化し、まとめ、さらに子どもたちを伸ばしていきたいという確かな思いである。「君には無理だ」と笑われることもきっとあるだろう。しかし、「いつか必ず死ぬ時が来る」
「毎日どんなことをしている日々が楽しいか」と、切実感をもって自問したとき、私は覚悟を決めた。自分の時間の使い方を見直した私は、今、毎日がより充実しているように感じている。
著者は次のようにいう。
時間をうまく使ったといえる唯一の基準は、自分に与えられた時間をしっかりと生き、限られた時間と能力のなかで、やれることをやったかどうかだ。(P.265)
あなたは、時間をうまく使えているだろうか。
読書日記~4月~

『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
齋藤孝 詩想社 2023年
『本質を把握するために』
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』というタイトルを見てドキッとした。
自分の話はどうだろうか…。
子どもの心を動かすような深い話ができるようになりたい。
しかし、そもそも、浅い話、深い話とはどのような話なのだろうか。
本書では、「聞いている側がまったく変化を起こさない、化学反応を起こさない話」を浅い話の典型として挙げている。反対に、「驚きや気づきがあったり、理解が深まったり憧れの気持ちを起こさせたりして聞き手側の感情の部分を刺激する話」を深い話だという。
そして、話の深さについては、次のように述べている。
結局、深さというものは、思考を重ねていくことでしかたどり着けないという面もあるのです。(p91)
ハッとさせられた。「たくさんのことを知っていれば、深い話をすることができる」と考えていたからである。話の深さには、その話をするまでにどれだけの思考を重ねたかが関係しているのだ。
たしかに、専門家や職人の話を「深い」と感じることは多い。専門家や職人など、その道を究めた人は、道を極めていく過程で多くの試行錯誤があり、考え抜いた経験があるから話に深さが出るのであろう。
「深さというものは思考を重ねていくことでしかたどり着けない」という視点を日常での学びに結びつけてはどうだろうか。例えば、読書。読書を通して初めて知ったことに対しても「なぜか」を考えたり、「自分なら」と考えたりするのである。
「話が深い」人になるために、日々の学び方を変えていこう、そう気付くことができた。
読書日記~2月その2~

『昆虫は美味い!』
内山昭一 新潮新書 2019年
『「認識が変わる」ということは』
「認識の変容」。子どもたちに道徳の授業を実施するにあたり,我々が常に意識していることではないだろうか。
来るべき食糧危機にそなえてなのか,近年話題となっている昆虫食。私もどんなものかと,某雑貨店でコオロギ入りのクッキーを,某味噌蔵元でコオロギ入り醤油をそれぞれ買って食してみた。ふむ,言われなければまったくわからない。これなら生活に取り入れていけるかも!そう思った矢先,この本と出会った。
カマキリが食用として美味しいのは卵である。・・・アルミホイルに包んで焼くと水っぽくならないでいい。醤油を少々たらしていただく。小粒だがほっこりした茹で卵の黄身の風味がする。 71頁
オオゴキブリは森に潜んで朽木を食べているから、家の中に出没する連中と違って臭みがほとんどない。揚げたてはエビの味がする。 92頁
なんということだ…。甘かった…。今の「なあんだ,パウダー状のものを混ぜるだけならいけるじゃん!」といった認識のままでは,昆虫食を生活に取り入れるなど,到底無理である。
食の好みについて、内山氏はこう述べている。
今でこそ高級寿司ネタとなったマグロのトロだが、大正時代以前は脂っこすぎると敬遠されていたという。・・・好きになるには、味に慣れる必要があるのだ。 46、47頁
慣れるということは、単に味に慣れるということだけではない。未知なるものを食すという行為に対しての慣れ、これまでの認識とは違う味を発見することへの慣れも含まれるのではないだろうか。
とは言え、私にはその「はじめの一歩」がなかなか重い。しかし,本の中に登場する,著者のワークショップに参加した子どもたちの好奇心はすさまじい。
斎藤君は帰ってから,自分でアブラゼミを捕まえて,素揚げにして塩で試食しているのがすごい。 195頁
また,子どもを見守り支援する親の立場からのコメントも,感服するばかり。
「人が社会的な生き物である以上、親の立場からは、その個性が社会の許容範囲であるかという側面からの考慮が必要であると考えますが、『皆さんがされていないこと』という理由だけでは、我が家の禁忌たりえません。」 199頁
これらの事例は,同じ日本でのこととは言え,特別なことなのだろうか。否。私は覚えている。山間部で暮らしていた祖父(享年82歳)が,「ごちそうだぞ!」と言って,蜂の子(ヘボ)を,酒の肴にしていたことを。「子どもの頃はニンジンが嫌いだった」と言っていた祖父が,どうして蜂の子(ヘボ)を好んでいたのか理解に苦しんだものだ。今こそ,当時成しえなかった,祖父の思いに迫る行動をとるべき時が来たのではないか。この本を読み,その思いがふつふつとわいてきた。
内山氏は、マーヴィン・ハリスの言葉を引用した。
「わたしたちが昆虫を食べないのは、昆虫がきたならしく、吐き気をもよおすからではない。そうではなく、わたしたちは昆虫を食べないがゆえに、それはきたならしく、吐き気をもよおすのである。」(『食と文化の謎』より) 199頁
普段、簡単に「認識の変容」などと語っている自分だが、それは容易く得られるものではなく、時として、勇気や覚悟を伴うということを突きつけられたような気がした。
さあ,来シーズンまで,「蜂の子(ヘボ)を食べてみよう!」というモチベーションが保てるのか。今まさに試されているようだ。机上ではなく、実体験による認識の変容を味わうまたとない機会を得たのである。
読書日記~2月~

『勉強がおもしろくなる瞬間』
パク・ソンヒョク ダイヤモンド社 2022年
『勉強の本質』
「どうして勉強をするのか。」
子どものときに親に聞いたことがある。
「将来、勉強したことが役に立つから」と言われたが、いまいち納得できなかった。
あなたが、同じように聞かれたらどのように答えるだろうか。
著者は勉強について、次のように言う。
勉強の本質は自分の魂を鍛え上げてくれることにあります。(87ページ)
勉強を通して自分の弱さと向き合い、その弱さを乗り越える経験を重ねることが自分の魂を鍛え上げることにつながるのである。では、自分の魂を鍛えることで、どんないいことがあるのだろうか。
著者は言う。
自分の運命を変える「挑戦」や、避けられない「困難」を前にしたとき、「強い魂を持った人」と「そうでない人」は、生死を分けるほど違います。(86ページ)
勉強をしていると嫌でも困難が訪れる。勉強している成果を感じられなかったり、どうしても勉強に向かう気力が起きなかったりすることがあるだろう。そのような困難を一つ一つ乗り越えていく経験をすることこそが勉強の本質なのではないだろうか。このようにして勉強を通して鍛えた魂が、人生の勝負所で自分を支える武器になるのである。
ふと、最近の自分はどのくらい勉強に取り組んできたのだろうかと考えさせられた。勉強は子どもだけがするべきものなのだろうか。そうではない、と自分は思う。子どもに勉強することの意味・良さを語ることができる教師であるためにも、自分の運命を変える挑戦のチャンスが訪れたときに後悔しないためにも、勉強し続けていきたいと思った。
読書日記~1月その2~

『絵を見る技術』
秋田麻早子 朝日出版社 2019年
『スキームと感性を働かせて、絵を見よう』
「絵を好きなように見ていいんですよ」
どのように絵を見ていいのか分からないから、その視点を聞いているのに、このようなことを言われたことはないだろうか。
美術史研究家の秋田氏は、次のようにいう。
絵の見方を知っている人は、目立つ箇所だけでなく、それと背景との「関係性」を意識して見ているのに対し、絵の見方のなじみのない人は、目につくところだけに注目しているのです。両者では、目の動かし方そのものが完全に違うということです。(11ページ)
絵の見方を知っている人とそうでない人との違いは、「目の動かし方」だそうだ。
例えば、前者は「輪郭線がある、ない」とか「この色が目立つ、あの形が目立つ」など造形的な要素を指摘するのに対し、後者は「明るい、暗い」という漠然とした印象を述べる傾向があるらしい。
以前、ゴッホ展に行った際、「ひまわり」という作品を生で見ることができた。写真などで見るのと違い、花の立体感に感動した。しかし、「花に立体感があった」としか周りに伝えることができなかった。花以外のところに目が行かなかったのである。私も「絵の見方のなじみのない人」と言えるだろう。
秋田氏は、「目の動かし方」という視点の他に、絵と向き合うポイント(スキーム)について述べている。
絵のデザインを要素ごとに分けて、それぞれの役割が何なのか、絵に問いかけながら見るということです。(23ページ)
なんということだろうか。
鈴木先生が道徳の授業づくりで主張している、教材を見るポイント(「構成要素に分け、その意味を見抜く」)と同じである。見るべき対象は違っても、本質を見抜くための視点は同じなのだろう。
さらに秋田氏はいう。
これらのスキームを知れば、絵がどんなふうにデザインされているものか分かります。そして、見て分かることを正確に観察できるようになり、名画の何がどうすごいのか、理屈の面からも理解できるでしょう。ひるがえって、自分が感じたことが、絵の何を見て得たものなのか分かるようになるのです。つまり、自分の感性がどういうものか、具体的に把握できるということです。(24ページ)
なんということだろう。
秋田氏の主張と鈴木氏の主張がほぼ同じである。鈴木氏は道徳授業づくりにおいて、教材を構成要素に分けて、その意味を問う作業をすると、その要素の存在意義やその要素に対する疑問をみいだすことができるので、その教材を深く理解することができると主張している。
絵画を見る視点と教材を見る視点に共通点があることを知って、絵を見ることがより楽しくなった。
感性を働かせて、感動を味わうことから名画を見ていきたい。
読書日記~1月~

『ドーパミン中毒』
アンナ・レンブケ 新潮社 2022年
『徹底的に正直でいる』
正直であることの良さとは?
と、問われたらあなたはどう答えるだろうか。
「信用してもらえる」「信頼関係が高まる」というように、人との関わりの視点で答えるのではないだろうか。
精神科医であり、本書の著者であるアンナ・レンブケ氏は、違う視点から答えている。
徹底的な正直さは自分の行為についての自覚を促す。(電子書籍版 p180)
正直に打ち明けることで自分の行動がはっきり見えるようになる。(電子書籍版 p180)
正直であることは自分の行動を正しく認知することにつながるのである。
アンナ氏は、ささいなことでも嘘をついてしまうと、自分の脳が勘違いを起こしてしまい、その内に、嘘の内容を話していても自分は真実を話していると錯覚してしまうようになるという。また、他者に対して正直であることは、自分にも正直であることと同じだということだ。
つまり、正直であることは自分を正しく知ることができるという良さがあるのである。自分を正しく知ることは、自分を成長させていく上でとても重要になるだろう。
では、どうしたら正直でいられるのだろうか。アンナ氏は言う。
徹底的に正直でいようとすることがそれに関わる神経回路を強化する (電子書籍 p182)
正直でいようとする判断を繰り返すうちに、正直でいようとすることが当たり前になっていくのである。つまり、正直でいようとすることを積み重ねることが、正直でいるために大切なのである。反対に、嘘をついてしまうと嘘をつくことが当たり前になっていってしまうのである。
正直でいるために大切なものは嘘をつかない心の美しさだけではなく、「正直でいる」と決める覚悟なのかもしれない。まずは短い期間からでも、「徹底的に正直でいる」ことを積み重ねようと思う。
読書日記~12月~

『プロの思考整理術』
和仁 達也 かんき出版 2021年
『アドバイスはおせっかい?』
教師という仕事をしていると、悩んでいる子どもを放っておけない。だから、気付いたら「もっとこうすればいいよ!」とアドバイスしていた、なんていうことがよくある。しかし、そのアドバイスが子どもたちの心に響くことは少ない。適切なアドバイスをしたつもりなのにどうしてだろうか。
トップコンサルタントの著者は次のように言う。
求められてもいないのにするアドバイスは“おせっかい”です。トップコンサルタントは、余計なアドバイスは一切しません。相手と一緒に考え、真の問題を見い出し、解決策は相手自身に見つけてもらいます。(電子書籍P.2)
なんてことだろう・・・。
ぼくがしていたことは、「おせっかい」だったのである。
悩んでいる人が望んでいることは、「誰かに悩みを解決してもらいたい」ではなく、「悩みを自分で解決したい」だったのである。スッキリするためには、自分自身で正解にたどり着いた実感や納得感が必要なのだ。
つまり、子どもが悩んでいるときに私が一番にするべきことは、「一緒に考えること」だったのである。子どもが悩んでいることについて、同じ目線に立ち、一緒に答えを探すことが大事だったのだ。その後で、「何が原因で悩んでいるか(=真の問題を見出す)」ということについて話を聞き、明らかにしていく。
例えば、友達との関係に悩みを抱えている子には、次のように寄り添ってみたい。
まず、モヤモヤしていることを肯定的に受け止める。
その後、「どのくらいの間、モヤモヤしているのかな」、「どんなときに1番モヤモヤするのかな」、など相手が話したことを深く掘り下げるような質問をして、一緒に悩みながら、真の課題に気づかせる。
現状を知ったあとに意識するとよいポイントについて本書では次のように書かれている。
意識が現状にとどまったままだと思考は停止してしまうので、いったん理想をイメージしてもらって思考を上向きにさせると、できる方法を考えるようになります。(電子書籍P.117)
「自分に100点をつけることができるのはどんな状態になったとき」、「どんな状態になるとスッキリすると思う」などと問いかけ、思考を上向きにさせ、子どもが解決策を見つけられるように導いていく。
もしかしたら、子どもが見付けた解決策は、子どもの悩みを聞いたときに教師は思い浮かんでいたものと同じかもしれない。しかし、子どもが自ら見つけたということに価値があるのである。解決までの早さだけに捉われずに、解決する過程も大事にする教育を心掛けようと思う。
読書日記~11月~

『日本酒で“KANPAI”』
久慈浩介 幻冬舎 2022年
『伝統や文化を継承する人々』
道徳の授業で「伝統や文化の尊重」を扱うとき、大切にしたい視点がある。
それは、人々を魅了する伝統や文化がもつ力と、それを継承しようとたゆまぬ努力を続けている人たちの存在である。
ただ人々を魅了する力があるだけでは、時代の変化や時の流れによっていつの間にか衰退し、忘れ去られてしまう。そこには必ず、「その素晴らしさを人々に伝えたい」、「後代まで残したい」と強く願い、継承していくために困難を乗り越えながら尽力する人々がいるのである。
本書の筆者は、岩手県二戸にある創業120年の老舗酒蔵「南部美人」の5代目蔵元、久慈浩介氏である。久慈氏は、時代の変化による日本酒需要の低下と東日本大震災といった数々の困難に直面してきた。それでも、代々受け継いできた主力商品である日本酒「南部美人」のブランド力を高めることを諦めなかった。久慈氏を突き動かしたものとは、一体なんだったのだろうか。
久慈氏は言う。
高く堅固な土台に、少量の柔らかい土を盛るのは難しいことではありません。それで満足していては、先代たちに申し訳ないという気持ちで私なりに頑張ってきました。先代たちがそうしてきてくれたように、南部美人の長き伝統によって築かれた土台を、私の代でより高く、より強固なものにして、息子の太陽に渡さなければならないのです。(p181)
伝統と家業を受け継ぐ蔵元として、それらを継承しようとする使命感。そして現状に満足せず、受け継いだ伝統をより良いものにして次代に引き渡そうという情熱。それらが、スパーリングの日本酒、急速冷凍技術を活用した生酒、そして糖類無添加梅酒などの新商品として身を結び、国内需要の低下に立ち向かうことができたのである。
久慈氏は次のようにも述べている。
新しいことに取り組むと、必ず何かしらの気づきや学びがあるのが常です。(p122)
長年受け継がれてきた伝統とは、同じことの繰り返しを意味するのではない。時には従来の常識を打ち破ることが、伝統産業を発展させることにもつながるのだと、久慈氏は考えている。
使命感や情熱から新たなことに挑戦しようとするとき、そこには常にあらたな気づきや学びがあり、それが更なる成長や発展につながっていくのだ。
日本には数々の人々を魅了し続けている伝統や文化がある。しかし、それらを継承するために奮闘し続けている人たちが必ずいることも、子どもたちに伝えていきたい。
読書日記~10月その2~

『感性のある人が習慣にしていること』
SHOWKO クロスメディア・パブリッシング 2022年
『感性を磨くことを習慣にする』
SDKでは「感性を磨く」と題したセミナーを定期的に行うほど、感性を磨くことを大切にしている。セミナーを通して私が学んだ感性の磨き方は、「何でもおもしろがる気持ちをもつこと」である。
では、世の中にいる鋭い感性をもっている人はどのようにして感性を磨いているのだろうか。
本の著書であるSHOWKO氏は、陶芸家であり、常に鋭い感性が求められる環境にいる。
SHOWKO氏は感性を養うために大切なこととして、次のように述べている。
どんなに細かい変化や違和感にも気づこうとする「観察する習慣」です。日々の生活を意識的に過ごし、これまで目を向けていなかったことを意識して見つめ、日常を解像度高くとらえてみましょう。(電子書籍p34)
「観察する」ではなく、「観察する習慣」を大事にしているということにハッとさせられた。
また、SHOWKO氏のいう「観察する」という例がとても興味深い。
それは、江戸時代に活躍した画家である伊藤若冲のエピソードである。
伊藤若冲は花鳥画を描く際に、一日中自宅で飼っている鶏を観察したという。
これまで目を向けていなかったことを意識して見つめることで、世の人を感動させられるような作品を描くことができたのであろう。
私がセミナーで学んだ「何でも面白がる気持ちをもつこと」も、アンテナをもっと高く張り、これまで目を向けていなかったことを意識すること。その意識を日々の生活で常にもとうとすることでさらにレベルアップさせることができるのではないかと気付かされた。
また、SHOWKO氏は言う。
感性を養う旅は、命が尽きるまで終わりません。 (電子書籍P270)
またしてもハッとさせられた。感性を養うことに終わりはないのである。だからこそ、感性を磨くことを習慣にして、感性を磨き続けることが大切なのだと考えさせられた。
読書日記~10月その1~

『伝える準備』
藤井貴彦 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021年
『自分の言葉がどんな印象を与えるか精査しながら発信する』
あなたは、日々の学級づくりのために、伝えたい言葉をどのように準備しているだろうか。
あなたが使った言葉は、子どもたちにどのように伝わっているのだろうか。
藤井氏は次のようにいう。
私たちアナウンサーは、自分の言葉がどんな印象を与えるか精査しながら、日々、発信しています。(6ページ)
この文を取り上げた理由は、「発信する前に自分の言葉が相手にどんな印象を与えているのかを精査している人は少ないのではないか」と思ったからである。
子どもの行動に価値ある印象を与えられるような言葉を準備することができれば、行動改善をより促すことができ、学級を成長させることができそうだと考えた。
では、伝えたい言葉をどのように準備すればいいのだろうか。
藤井氏は、次のようにいう。
責任を持つというスタンスを取ることで、自分に変化が生まれるということなのです。実際、勢いだけの言葉選びは減りますし、潔い言動が増えてくるはずです。(162ページ)
先日、ささやかな子どもの行動に対して次のような言葉を伝えた。
「給食の準備が10分を切るようになってきたね。すごいなぁ」
子どもたちは自分の言葉をどう受け取っただろうか。
もしかしたら、子どもたちには「10分切り」という言葉だけが残ってしまったかもしれない。
反省である。
「白衣に着替える前のテキパキした行動が、食べる時間の確保につながっているね」という行動変容とその効果に焦点を当てた言葉をはっきりと伝えるべきだった。
藤井氏の言葉を知ってからは、言葉を発した後も自分の言葉を子どもたちがどう受け止めたのかを考えるようになった。
藤井氏は、さらにいう。
ほんのわずかな伝える準備で、自分の周りのみなさんの表情が変わっていきます。その表情に囲まれたあなた自身も、さらにいい変化を見せ始めるでしょう。(8ページ)
精査しながら発信し続けることで、周りと自分のいい変化をつくっていきたい。
読書日記~9月~

『エフォートレス思考』
グレッグ・マキューン かんき出版 2021年
『今、この瞬間』
難しいのは、聞くことではない。聞きながらその他のことを考えないことだ。
難しいのは、その場にいることではない。そこにいながら過去の出来事や未来の予定に気を取られないことだ。(電子書籍97ページ)
この文章を読んだときにハッとさせられた。
何かをしながら、別のことをする方が難しく、また、二つ以上のことを同時にできることこそが効率的に物事を進める秘訣なのではないかと考えていたからである。
最近の書店では、「効率化」や「無駄を減らす」といった言葉が書かれた本が目立つところに置かれていることが多いように感じる。自分自身そのような本を見つけたときには「何だろう」と思い、興味をもつ。
しかし、自分は何のために「効率化」をしたかったのだろうか。
目の前の一瞬を大切にする余裕がほしかったのではなかったのだろうか。目の前の一瞬を大切にする時間を確保するために、目の前の一瞬を大切にできていないという矛盾が起こっていなかっただろうか。
私は「効率化」を意識するあまり、いつのまにか一つのことに集中することの大切さを忘れてしまったようである。だからこそグレッグ氏の言葉がとても心に響いた。
一つのことに集中することの大切さをグレックは次のように述べている。
人の存在は、大きな力をもつ。全身全霊でその場にいるとき、そして全力で相手に向き合うとき、私たちの存在自体が、相手に予想もしないほどのインパクトを与えることがある。(電子書籍103ページ)
自分は子どもの前にいるとき、全身全霊でその場に「いた」だろうか。子どもと全力で向き合っていただろうか。心の中で「この後は…」、「クラスのためには…」といったことを考えていることがなかっただろうか。
子どもたちのために…と様々な教育技術を学ぶことや、効率的に業務を進めていくことは悪いことではない。必要なことである。しかし、それ「だけ」になることがないようにしなければと考え直すきっかけになった。何のための学びで、何のための効率化なのか、本質を見誤らないようにしたい。
読書日記~8月その3~

『「させていただく」の使い方』
椎名美智 角川新書 2022年
『研究者の姿勢から学ぶ』
最近よく耳にするようになった「させていただく」という表現。
そのちょっとした表現に着目し、なぜ人々がこの表現を使うようになったのか、その理由を追究した成果をまとめて解説したのが本書である。
その理由も興味深いが、今回は、この著者から学べる「道徳教育の評価に活かせる視点」を紹介させていただく。
椎名氏は述べる。
「させていただく」という言い方は、多くの人に広く使われています。もちろん違和感を覚えるとの意見も少なからずあるわけですから、その言い方を分解して分析するのは重要なことです。 (p89)
日常的によく使われているにも関わらず、人々が違和感を覚えるような表現に着目し、その表現が好まれるようになった要因を社会の変化、人々の意識の変化、そして日本語の敬語の変化に焦点を当て探っているのである。
椎名氏から学べることは、ささやかな言動を受け止める鋭い感性と、その重要性である。
道徳教育の評価においても、教師が子どもたちのささやかな言動を捉えようとする姿勢が欠かせない。
授業後の子どもたちに変容が見られたとしても、その何気ない一言や、ちょっとした行動を捉える力が教師になければ、適切に評価することはできないからである。
さらに、椎名氏は捉えた言動を、人々の意識の変化と結びつけて、次のように述べている。
人々の匿名性が高まり、(中略)私たちは対面する相手をどのように遇すればよいのかわからなくなります。そういうとき、人々は相手に失礼のないように、そして自分がちゃんとした人間であることを示すために、寄る辺なく敬意にすがり、新しい表現方法として「させていただく」を見出したのではないかと考えたくなります。(p89)
「させていただく」という表現の使用に、対人関係をより円滑にする働きという価値を見出し、意味づけている。
ここから、子どもたちのちょっとした一言や行動にどのような道徳的な価値があるのかを、教師が的確に意味づけることの必要性を学ぶことができる。
学級通信や学級の時間を活用して、その意味づけを学級全体で共有することで、その価値が浸透していき、個人や学級全体の成長につながっていく。
道徳の授業だけで終わるのではなく、道徳教育の評価も子どもの変容をさらに促す手立てとして活用していきたい。
読書日記~8月その2~

『バナナの魅力を100文字で伝えてください』
柿内尚文 かんき出版 2021年
『伝えると伝わる』
教師は日々子どもたちに多くのことを「伝え」ようとする。
しかし、どのくらい「伝わって」いるのだろうか。
「伝える」と「伝わる」の間には大きな壁がある。視点の違いから生まれる壁である。
「伝える」は話し手視点の言葉であり、「伝わる」は聞き手視点を取り入れた言葉である。
「伝わる」ということについて、柿内氏は次のように述べている。
伝わるとは、伝えたい相手の心に「印象+記憶」を残すことでもあります。(電子書籍p46)
柿内氏の主張を基に考えると、伝えたいことを話すだけでは、相手に伝わらないということになる。印象を残すことが大事なのである。話をしているときに相手に届くのは言葉だけではない。目線、身振り、表情といったことに加え、立場や状況などあらゆることをメッセージの一部として聞き手は受け取る。それらの要素のどこかでギャップを感じさせたり、好意をもたせたりすることができれば伝えたいことの印象を残すことができる。
また、記憶に残すために必要な大きな要素の一つは、「納得感」である。印象に残った話について、「なるほど」や「確かにそうだ」と感じた度合いにより、記憶への残り方は変わる。
私を含め、教師という職に就いている人は、人に何かを伝える場が多々ある。そこで大切なことは、その気持ちをそのまま出すのではなく、どうしたら「伝わるのか」=「印象+記憶にのこるのか」を思考することである。
柿内氏は以下のようにも述べている。
伝え方というと、「どう話すか」「どう伝えるか」というアウトプットに意識がいきがちですが、聞く力や親近感も「伝わる」の大切な要素です。(電子書籍p63)
伝わるためにはどうしたらよいかを考えるときには、話すときの工夫を一番に考えがちではないだろうか。しかし、柿本氏は、聞く力や親近感も大切であると述べている。つまり、教師として「伝わる」話をするために工夫するべきことは、伝えたい話をするその瞬間だけではないということだ。
自分の話が子どもたちに伝わらないときは、伝え方を見直すだけでなく、自分の指導法や関わり方も見直してみてはいかがだろうか。
読書日記~8月その1~

『歴史思考 世界史を俯瞰して、思い込みから自分を解放する』
深井 龍之介 ダイヤモンド社 2022年
『当たり前を疑う』
歴史上には、たくさんの偉人がいる。
偉人を扱う道徳授業を開発するとき、偉人の素晴らしい功績を目にするが、「それに引き換え自分は・・・」と自信を失ってしまう人も多いだろう。
私がその一人だ。
しかし、偉人たちは、本当に偉かったのだろうか。優秀で、清廉潔白で、完璧な人だったのだろうか。
深井氏は、歴史を俯瞰する見方として、次の2点を示している。
人間の評価を、短期的なスパンで下すことにあまり意味はない(p27)
かの有名なカーネル・サンダースが、ケンタッキー・フライドチキンを創業したのは、65歳。それまでのサンダースの人生は、事業に失敗し、2度も破産している。そこだけを切り取って見ると「なんて不幸な人生なんだ。」と思うだろう。
このように、歴史上の偉業なんて、どこで切るかで評価は大きく変わってくるのである。
人の価値観は絶対ではなく、場所や時代によって変わる(p18)
ソクラテスも織田信長も、多くの歴史上の偉人が同性愛を経験している。
人類史を見ると、男性同士の恋愛は当たり前だった。それがなぜ、同性愛が特殊で、否定的なイメージをもたれるようになったのか。
それは、キリスト教の影響である。キリスト教の拡大とともに、同性愛を否定する考え方が広まっていった。
このように、現代では少数に見えることが、実は歴史の中では一般的だったことがたくさん存在する。
深井氏は、歴史を知るというのは、
私たちの「当たり前」が当たり前ではないことを理解すること
だという。
歴史を俯瞰して、「当たり前」という思い込みから自分を解放すれば、目の前にある悩みにとらわれずに済むこともあるはずである。だからなのか、この本を読んだ後、自分の悩みがちっぽけに感じ、楽に生きるヒントをもらったような気持ちになった。
読書日記~7月~

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』
山口周 光文社新書 2017年
『美意識を鍛えることと授業づくり』
今、世界のエリートは「美意識」を鍛えることに目を向け始めているのだという。
これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできない、ということをよくわかっているからです。(p14)
もちろん、論理的に因果関係を考えたり、数値等を分析して問題解決を図ったりする「サイエンス重視の意思決定」も重要である。
しかし、多くの人がそうした問題解決能力を身につけた結果、似たような解決策しか見出すことができず、逆に他との差別化を図ることが必要になってきているからだという。
そこで重要になるのが、「直感」や「感性」という「美意識」なのである。
「フワッ」と浮かんだアイデアが優れたものであるかどうかを判断するためには、結局のところ、それが「美しいかどうか」という判断、つまり美意識が重要になるからです。(p88)
論理的、分析的な思考だけでなく、「美しい」「いい」「心に響く」というような「美意識」で判断することが、差別化を図り、オリジナリティやユニークさのあるアイデアにつながるのだ。
これは、小さな道徳授業づくりにもいえることではないだろうか。
ポスターや看板などを見て、「フワッ」とした教材化のアイデアが思い浮かぶことがある。
そこで、「美意識」を基準にそのアイデアの優劣を判断することは、子どもたちを惹きつけたりワクワクさせたりするような素材を精選することにつながるのではないだろうか。
では、「美意識」をどのように鍛えることができるのか。
山口氏はその方法として、次の4つを提案している。(p211)
① 絵画を見る ② 哲学に親しむ ③ 文学を読む ④ 詩を読む
例えば絵画を見るときに、「何が描かれているのだろうか」「絵の中で何が起きていて、これから何が起こるのだろうか」「自分の中にどのような感情や感覚が生まれているだろうか」と自問自答することで、ちょっとしたヒントから洞察を得る観察力を向上させることができる。
そうした観察力は、身近にある素材や教材の構成要素に気付くために必要な力でもある。
「直感」や「感性」という美意識を鍛えることは、授業づくりという教師の力量を高めることにもつながるのである。
読書日記~5月~

『心理的安全性のつくりかた』
石井遼介 JMAM 2020年
『 よりよい学級づくりのために』
近年、ビジネスの世界で効率的な組織・チームを作るために重要とされている概念に、「心理的安全性」がある。
石井氏はその概念を次のように定義づけている。
組織やチーム全体の成果に向けた、率直な意見、素朴な質問、そして違和感の指摘が、いつでも、誰もが気兼ねなく言えること(p3)
これは、学級という組織・チームをつくる教育現場でも重要な概念ではないだろうか。
石井氏によると、ある要因があると「心理的安全性」を確保できないという。
それは、「対人関係リスク」である。
チームにおいて、自分の発言や行動について、他の人から「こんなふうに思われるかもしれない」とか、「あとで何か言われたりされたりするかもしれない」と不安を抱えてしまう状態のことである。
そのような「心理的『非』安全」な集団では、挑戦することがリスクとなるため、行動を起こすことができなくなり、個々の気づきや知識をうまく集団の財産へと変えることができないのである。
では、どうしたら「心理的安全性」を確保できるのか。
石井氏は、次の4つの因子があるとき、心理的安全性が感じられるという。(p49)
①話しやすさ ②助け合い ③挑戦 ④新奇歓迎
何を言っても大丈夫という「話しやすさ」があり、困ったときはお互い様と考えて建設的に解決策を模索して「助け合い」、とりあえずやってみようと「挑戦」し、個々の強みや個性など「新奇歓迎」する集団は、高い心理的安全性が確保されるのである。
学級経営において、教師は①②③④を実現させるために何ができるだろうか。
例えば、学級における「話しやすさ」を高めるためには、まずは教師が子どもの発言を肯定的に受け止める姿勢が大切である。
発言を求めるときにも、「意見を共有してくれますか」「自分の考えをペアやグループで共有しましょう」と投げかけることで、お互いの意見や考えを学級全体で共有しようとする雰囲気を醸成することができる。
そうした土台を生かして、お互いを素直に認め合い、肯定的な声をかけあえる学級づくりをねらいとして「小さな道徳授業」を行うこともできるだろう。例えば、鈴木健二編著『学級経営に生きる 5分でできる 小さな道徳授業1』に掲載の「すなおに言える?」(p58、59)である。
では、残る②③④の因子を高めるために、あなたならどんな「小さな道徳授業」や学級活動を仕掛けたいと思われるだろうか。
読書日記~4月 その2~

『ヘーゲル哲学に学ぶ考え抜く力』
川瀬和也 光文社新書 2022年
『 考え抜く力を身につける』
「人生100年時代」といわれ、これまで以上に企業・組織・社会との関わりが長くなっていく。
そのような時代に活躍し続けるために社会人に求められる基礎力の一つが、「考え抜く力」なのだそうだ(「人生100年時代の社会人基礎力」経済産業省)。
常に問題意識をもって課題を発見し、どうすれば解決できるのかと疑問をもって、自律的に深く考える力。そんな「考え抜く力」を、私たちはどうすれば身につけられるのだろうか。
川瀬氏は、「近代哲学の完成者」と称されるヘーゲルの哲学を援用しながら、私たちの目に映る「現れ」と、物事の「本質」の次のような関係を理解することが大切だという。
把握しやすいが移ろいゆく「現れ」と、捉えにくいが確固とした「本質」は互いを支え合って存在している。(p156)
目に見える「現れ」を注意深く観察し、その課題や解決策を深く考えることで、その向こうにある物事の「本質」に迫ることができるようになるのだと、川瀬氏は説く。
これは、道徳の授業づくりにも当てはまるのではないか。
特に、現代的な課題に対応する道徳授業を開発するとき、目に見える課題ばかりに目がいってしまい、その表面的な解決策について考えようとしてしまいがちである。例えばヘイトスピーチやごみのポイ捨てという「現れ」の向こうには、誰にも存在しうる差別意識やいっときの無責任さという「本質」がある。その「本質」に迫ることで、授業の質が高まり、子どもの認識の変容を促せるのではないだろうか。
さらに考え抜くためのステップについて、川瀬氏は次のように述べている。
第一に、常に新たな知識を取り入れ続けることである。そして第二に、知り得たこと同士の結びつきを考えることである。(p263)
常に新たな知識を取り入れることで、「現れ」の新たな側面をより丁寧に認識することができるようになる。しかし、それだけではなく、取り入れた新たな知識同士の結びつきを考えたり、自分の経験や既知の知識と照らし合わせたりすることで、より柔軟な発想が可能になるのだという。
これは、新たな道徳授業を生み出すステップと共通している。
身近な素材を収集し続けることによって、世の中の見え方が少しずつ深くなっていく。それは、素材同士の新たな関連の発見や教科書教材との効果的な連動への気づきをもたらす。
「考え抜く力」を身につけようとする意識は、道徳授業の質の向上につながることだろう。
読書日記~4月 その1~

『バイアスとは何か』
藤田政博 ちくま新書 2021年
『バイアスと上手く付き合う』
毎日、たくさんの子どもたちと接する教師。
日々の関わりを通して、子どもたちをよりよく理解しようと努め、そうした理解や認識を指導や授業づくりに活かすことで、教育効果を高めることもできる。
しかし、もしその理解や認識がゆがんでいたとしたら、指導や評価にどんな影響を及ぼすのだろうか。
そうした、「物事を現実とは異なるゆがんだかたちで認識してしまう現象」こそが、本書が扱う「バイアス」である。
例えば、次のようなものがある。
【確証バイアス】仮説を証明したいという思いから、自分の仮説にあった事実をピックアップしてしまうバイアス(p100)
「この手立てを講じれば、子どもたちにこのような変容が見られるだろう」。
「この練習方法を取り入れれば、確実に力がついて、目標を達成できるだろう」。
そうした思いが強ければ強いほど、その仮説にあった子どもの姿に目を留めてしまうのである。
たとえ、悩んでいたり、否定的な反応を示していたりする子どもがいたとしても、そのことに気づくことができないのである。
また、次のようなバイアスもある。
【錯誤相関】相手をカテゴライズして、目立つものどうしが実際以上に強く結びついていると認知してしまうバイアス(p124)
藤田氏が紹介する実験結果からすると、少数派のグループの行動は、それが望ましい行動であっても望ましくない行動であっても、見かける頻度が少ないがゆえに、目立つ行動と判断されてしまうという。
気になる少数グループの言動を、過度に望ましくない方向に認知しないように注意する必要がある。
藤田氏は、バイアスについて知ることの意義を次のように述べている。
意識的選択や意思決定を行う際に「自分がそれに基づいて判断しようとしている情報には、バイアスによるかたよりが含まれているのではないか?と考え直すことで、意思決定の際に不都合なかたよりに影響されたままにならずに済むようになることもあります。(p48)
自分の思い込みや、現実とは異なるゆがんだ認識による指導や評価をすれば、子どもを置き去りにした授業をしたり、子どもを傷つけたり、信頼関係を損なったりしてしまう可能性もある。
「今の自分は、バイアスに影響されていないだろうか?」と、ちょっと立ち止まって考えたくなる。
読書日記~3月~

『おとなになるのび太たちへ』
まんが 藤子・F・不二雄/選 猪子寿之 梅原大吾 梶裕貴 亀山達矢 菅田将暉 田村優
辻村深月 なかしましほ はなお 向井千秋 / 小学館 2020年
『世界を変えるもの』
「あやとり世界。」
国民的人気マンガ「ドラえもん」で描かれる1つのストーリーである。ある日、のび太は特技のあやとりで新技を開発する。しかし誰にも相手にされない。そこで、「もしもボックス」を使ってあやとりが大流行している世界をつくる、という話である。
そんな「あやとり世界」を自分の人生に照らして紹介するのが、eスポーツプレーヤーの梅原大五氏である。
数年前まで、ゲームは、あやとりと同じように取るに足らない、ちょっとした暇つぶしのような存在でした。むしろ「ゲームは悪いもの」と思われていて、ゲームをやっていると怒られたりもしていたのに、最近では「ゲームはそんなに悪くない。仕事にもなるらしい」ということになって、突然手の平を返したように、「すごいですね!」と賞賛されるようになりました。
自分の特技がなかなか評価されない状態から、世界の方がガラリと一変する、まさしく「あやとり世界」のような体験をしている人物が実際にいたのである。
しかしこの例は、世界がたまたま運良くガラリと変わったというだけの話ではない。
梅原氏はいう。
それは趣味だろうが仕事だろうが、なんだろうが、みんなが諦めちゃうところで、もうちょっと、倍くらいやってみるとか3倍くらいやってみるとか、そうすると、景色が変わってくるっていうのが、実体験としてあります。
もちろん運の良さもあるだろうが、それは”2倍、3倍のもうちょっと”の継続に支えられているということである。”もうちょっと”の積み重ねこそが、梅原氏をゲームが認められる世界へ導いたのである。
梅原氏は17歳のときに世界大会で優勝している。
一人の少年の”2倍、3倍のもうちょっと”の積み重ねが結果を生み、世界を驚かせたのである。それはきっと、ライバルのプロゲーマーを奮い立たせ、多くの新たなプロゲーマーを生み出すことにつながったのではないかと思う。
そうした”2倍、3倍のもうちょっと”を積み重ねる人たちによって、世界は変わっていくのである。
諦めるな!やり続けよう!
実体験をもつ梅原氏の言葉は、重く簡単なものではない。しかし今自分が取り組んでいる端から見れば些細な仕事や趣味に、”2倍、3倍のもうちょっと”を加えたら…、と希望を抱かせてくれる。
読書日記~2月~

『「大発見」の思考法 ~iPS細胞vs.素粒子~』
山中伸弥 益川敏英 文春新書 2011年
『研究者に必要な才能』
教育実習のときに指導教官から言われた話が今でも心に残っている。
教師には3つの顔がある。1つ目は、役者の顔。2つ目は、医者の顔。3つ目は、研究者の顔。
子どもの前での振る舞い方、子どもの見取り方、授業のつくり方、指導教官が教職の心構えを教えるために分かりやすいと考え、話してくれたのである。
指導教官によれば、教師の3つ目の顔「研究者」。
“研究者に必要な才能”と言われれば、何を思い浮かべるであろうか。
新たな発想を生み出す想像力か、根気よく研究し続ける忍耐力か、それとも研究結果を正確にまとめ、報告する誠実さか。
iPS細胞を世に送り出した世界的研究者である山中伸弥氏は次のようにいう。
自分のやった実験の結果を見て、「うわ、すごい!」って面白がれる人じゃないと、研究を続けていくのは、難しいと思うんです。そこで、心からびっくりできる、感動できるというのが、研究者に必要な才能だと思います。(p90)
「うわ、すごい!」と面白がる才能がなぜ必要なのか。山中氏はこう続ける。
実験なんて予想通りにいかないことのほうが多いですから。私は学生にこう言っているんです。「野球では打率三割は大打者だけど、研究では仮説の一割が的中すればたいしたもんや。二割打者なら、すごい研究者。三割打者だったら、逆にちょっとおかしいんちゃうかなと心配になってくる。『実験データをごまかしていないか?』と言いたくなるくらいや」と。
仮説の的中率が三割を超えるというのは、本当に稀なことです。普通はそんなにうまいこといくわけがない。
むしろ、予想通りではないところに、とても面白いことが潜んでいるのが科学です。それを素直に「あ、すごい!」と感じ取れることが大切だと思います。(p99)
山中氏の考えを「研究者」としての教師に当てはめてみるとどうだろうか。
教材研究をする「研究者」であるとき、自分がどれだけの「うわ、すごい!」に出合う努力をしているだろうか。研究授業をする「研究者」であるとき、子どもの思わぬ反応をどれだけ「うわ、すごい!」と受け止めているだろうか。研究結果について、「実験データをごまかしていないか?」と言われるような研究になっていないだろうか。研究の失敗に感動できているのだろうか。
iPS細胞は、がん細胞の研究の失敗がきっかけで生まれたという。当時のボスが予想を外してがっかりしている中、未知との出合いに感動した山中氏の才能が、「大発見」を生んだのである。
読書日記~1月~

『深く考える力』
田坂広志 PHP新書 2018年
『敵は、我にあり。』
「深く考える力」は、どのようにすれば身につけることができるだろうか。
そのヒントとなるエピソードが本に紹介されている。
プロ野球選手の若手選手が、張本勲氏に理想のバッティング・フォームを尋ねたエピソードである。
「張本さん、理想のバッティング・フォームについて、教えて頂きたいのですが」
この質問に対して、張本選手は、こう答えた。
「理想のバッティング・フォームか。もし、君がそれを知りたいのならば、一晩中、素振りをしなさい。一晩中、素振りをし続けて、疲れ果てたときに出てくるフォーム、それが、君にとって一番、無理のない理想のフォームだよ」(P.88)
著者の田坂氏のよれば、このエピソードが”大切なこと”を教えてくれるという。
”優れた授業”や”優れた学級経営”の「答え」を求めて書籍を買ってしまった経験がある。
セミナーで配布された資料教材について、「自分ならどう授業するか」をよく考えもせず、講師の示す展開の「答え」を速く知りたいと期待してしまった経験。
あるセミナーで中学年向けの道徳授業を提案したとき、参加者から次のように尋ねられたことがある。
「これを低学年向けにアレンジするとしたら、どんな展開にしますか」
私は答えに詰まってしまった。担任する中学年の子どもを想定し、試行錯誤を重ねた結果の提案だったからである。
この質問者もまた、「答え」を求めていたのだろう。
「答え」を安易に他者にもとめてしまうことは、私に限らずあるようだ。
田坂氏はいう。
永年の体験と厳しい修練を通じてしか掴むことのできない深い「智恵」を、単なる「知識」として学んだだけで、その「智恵」を身につけたと思い込んでしまう。(P.86)
『「智恵」を身につけた』という思い込みは恐ろしいものである。
敵は、我にあり。(P.89)
他者から得た「知識」をいかに自分の「知恵」へと変えていくか。自分が何を思い出し、何を思いつき、何に悩むのか。「深く考える力」を身につけるための第一歩は、『「智恵」を身につけた』という思い込みに陥っていないかどうかを、常に自問自答し続けることにある。
開催予定
| 2025年4月12日(土) | 13:30~17:00 | SDK6周年記念大会 |
|---|