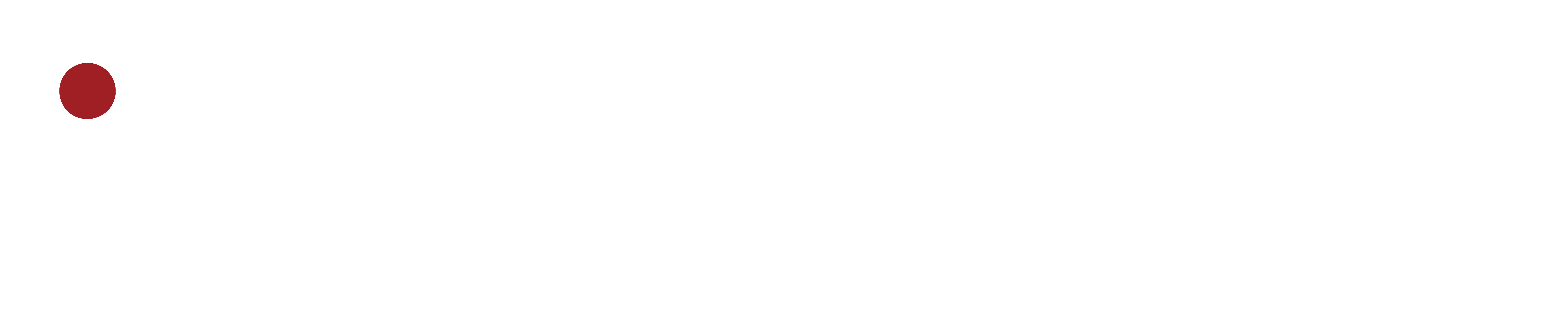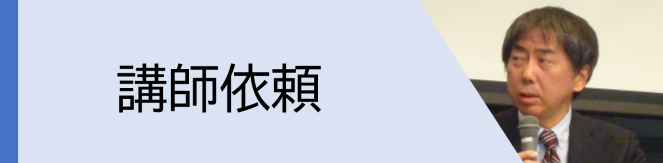漫言放語 №61
道徳教育の重要性を再認識する~新年度のスタートにあたって~
教育原論、教育課程論。
「どこかで聞いたことがあるな~」と思う教師も多いだろう。
教育学部では必修の授業である。
私も「どこかで聞いたことがあるな~」と思う教師の一人だったのだが、この2つの授業を4月から担当することになってしまった(頼まれた仕事は断らない主義?)。
というわけで、これまで一度も担当したことのなかった授業をゼロから構想していかなければならなくなった(おかげで3月は春の訪れを楽しむどころではなかった)。
しかし、新しいことに挑戦するといいこともある。
これまで書棚の奥深く眠っていた蔵書を何冊も引っ張り出し、読み直すことによって、新たな学びがいくつもあったのである。
読み直した本の一冊が、野口芳宏 第二著作集 国語修業・人間修業 第5巻『学校づくりの修業』(明治図書)である。野口氏は言う。
道徳教育が一番大切だ
このように野口氏が主張するのには、私たち教師が心に刻み込むべき重要な理由がある。
どれくらいの教師が、野口氏のような教育観をもって道徳教育を行ってきたのだろうか?ほとんどいないのではないかと思う。
いよいよ新年度がスタートする。
この一年間の道徳教育を充実させるにはどうしたらいいのか。
野口氏の主張に真正面から向き合う道徳教育をどのように構築していけばいいのか。
これは、6周年を迎えるSDKが追究していきたい大きな課題でもある。
SDK創立6周年記念大会では、この課題の解決に少しでも迫ることができるような提案をしたいと考えている。日時とテーマは次のとおり。
日 時 2025年4月12日(土)13:00~17:00
会 場 愛知教育大学教育未来館2階
テーマ 「小さな道徳授業」を効果的に活用するⅡ
~教科書教材と連動させて効果を高める~
新年度の記念大会は、野口氏の主張に向き合うところからスタートする。
おすすめリンク集
新着情報
開催予定
| 2025年4月12日(土) | 13:30~17:00 | SDK6周年記念大会 |
|---|